| 黒い夏【改訂版】 作:toshi9 イラスト:◎◎◎さん 立っているだけで汗が噴き出してくるような暑い夏のある午後、 突然恋人の山口さおりに呼び出された三浦祐二は、彼女の部屋を訪れていた。 インターホンを鳴らすと部屋のドアが開き、さおりが顔を出す。 「ごめん、遅くなった。待ったかい?」 「ううん、大丈夫だ……よ。それより中に入って」 にこやかに迎え入れたさおりは祐二を座らせた。そして冷蔵庫の中からよく冷えたペットボトル入りのジュースを取り出すと、グラスに開けた。 「汗びっしょりよ。ほら、これどうぞ」 さおりは黒いジュースを入れたグラスを祐二の前に置いた。  「サンキュー、あれ? さおりは飲まないの?」 「うん、あたしはさっき飲んだばかりだから。美味しかったよ」 「そうか、じゃあ遠慮なくいただくよ」 祐二はグラスを手に取ると、口に寄せた。そして彼が口をつけた瞬間、さおりはわずかにその唇をにやっと歪ませた。 ごくっ、ごくっ 「ぷはぁ〜、どろっとしているコーラか。変わってるけど旨いな」 「ふふっ、そうだね」 ガタッ 「あれ? 何か音が」 「ネズミでしょう?」 「おいおい、ネズミって、このマンションまだ新しいだろう」 「いいじゃない、そんなこと」 「いや、やけに大きな音だったし、それにドレッサーの中からだったぞ。大丈夫なのか?」 「ふん、大きなネズミなんでしょう、気にすることないわよ」 「大きなネズミって……う、うぐぅ」 突然胸を押さえて苦しみ出す祐二。そして彼はその場にばったりと倒れてしまった。 「ふふん、効いてきたようだな」 立ち上がったさおりは、無表情に祐二を見下ろした。そしてテーブルに置いたペットボトルを手に取ると、中に残ったジュースを造作なく捨ててしまった。  やがて彼女の目の前で祐二の体は段々と膨らみを無くし、萎んでいった。 「間抜けな奴だぜ。いくら僕がさおりちゃんの姿をしているからって自分の恋人かそうでないか位わからないのかよ。まあそれだけ僕の演技が大したものだってことか。さて……と」 奇妙な形のナイフを取り出したさおりは、萎んでしまった祐二の体から服を脱がすと、その腹をさっと切り裂いた。 「……ふふふ、出てきて出てきた。すっかりゼリーになっちゃって」 さおりは祐二の体から出てきたゼリーを丁寧にキッチンから持ってきたボールに移し取った。 「どうだいこいつは僕のことをさおりちゃんだと思い込んでたぞ。君が信じてた愛なんてそんなものさ」 そう言いながらさおりがドレッサーを開けると、中から子犬が飛び出してきた。 「きゃん、きゃんきゃん」 「うるさいなあ、体を返せとでも言ってるのかい? うふふ、駄目だよ。この顔、この体、さおりちゃんの全てはもう僕のものなんだ」 子犬に向かって微笑むさおり。そんなさおりに子犬は吼え続けた。  話は1時間ほど遡る。 「あら、松田君じゃない」 山口さおりがドアホーンのディスプレイを覗くと、扉の向こうに会社の同僚の松田高志が立っていた。 「急にどうしたの、松田君。さ、上がって」 無防備に高志を部屋に上げるさゆり。 小柄で大人しい高志は会社で女子社員からペット的存在として扱われていたのだから、 それもまあ当然なのかもしれない。 だがこの日の高志は、いつもの大人しい彼とは少し違っていた。 「さおりちゃん、君に聞きたいことがあるんだ」 「聞きたいこと?」 「三浦と付き合っているのかい?」 「え? どうして?」 「昨日見たんだよ。君とあいつが楽しそうに腕を組んで歩いているのを」 「ふん、そんなことあなたには関係ないでしょう」 「そ、それは……」 「あたしは彼のことを愛してるし、彼もあたしのことを愛してくれてるのよ、ね、ジョン」 「わん」 少しだけ頬を赤くするさおり。 さおりのペットの子犬が相槌を打つように一声吼える。 「そうか、わかったよ。ところで、今日は面白い飲み物を見つけたんで、一緒に飲まないかと思って持ってきたんだ」 「面白い飲み物?」 「ジュースなのにぜりーみたいにプヨプヨしてるんだ」 「へぇ〜」 「ほら、これさ。グラス出してくれる?」 トートバッグからペットボトルを取り出す高志。 唐突な高志の話に訝しく思いながらも、高志のことを人畜無害としか思ってないさおりは やれやれとばかりにキッチンからグラスを二つ持ってきた。 「ほら、面白いだろう、しかもこれがおいしいんだ」 ペットボトルを開けて、むりむりと中身を押し出す高志。ゼリー状の中身がゆっくりとグラスに注がれる。 「ほんとだ、変わってるのね」 「はい、飲んで」 「ありがと、ふ〜ん、コーラ味なのにゼリーみたい」 「そうさ。しかもこれには面白い効果があるんだ」 「面白い? あぐっ」 突然胸を押さえて苦しみだすさゆり。そして彼女はその場に崩れるように倒れてしまった。 やがて彼女の体は中身を無くしたかのように、萎びるように縮んでいく。 「ふふふ、やったぞ、これでさおりちゃんの体は……」 高志はトートバッグから奇妙な形のナイフを取り出すと、さおりの上着を脱がせて腹部をさっと切り裂いた。 切り開かれた切り口からは、血ではなく、どろりと黒いゼリー状のものが溢れ出ててくる。 それを高志はキッチンから持ってきたボールに移すと、不思議そうに見ていた子犬に飲ませてしまった。 「わん!?」 子犬がゼリーを食べ終えると、その瞳に知的な光が宿った。そしてきょろきょろと辺りを見回し始めた。 やがて自分の前に立っている高志に気がついた子犬は、高志を見上げて驚いたようにぽかんと口を開いた。 「きゃんきゃん」 「こんにちは、子犬のさおりちゃん。くくっ、どうだい? 子犬になった気分は」 四つんばいでしか歩けない。しかも自分の声が犬の鳴き声にしかならない。 子犬になってしまったさおりは混乱してぐるぐると歩き回った。 「わ、わん?」 「僕の気持ちも知らないで、三浦なんかと付き合うからこんなことになるんだ。 後悔してももう遅いよ。これはもう僕のモノだ。今日から僕が君になるのさ」 自分勝手な理屈を並べながら服を脱いだ高志は、すっかりぺしゃんこになったさおりの抜け殻から下着を外すと、 開いた切り口を押し広げて体を潜り込ませ始めた。 両腕、両脚、そして腰、腹、胸、首を体にさゆりの抜け殻を自分の体にフィットさせていく。 そして最後に長い黒髪のさおりの頭の中に、自分の頭をすっぽりと納めた。 高志の全身が完全にさおりの抜け殻の中に納まると、開いていた切り口は閉じ始めた。 それと同時に高志が被ったさゆりの抜け殻が変化していく。 シワの寄った皮膚につやが出る。腰がくびれていく。萎んでいた胸がふくよかに膨らんでいく。お尻がぷりっと張っていく。 やがてさおりの抜け殻が高志の体に馴染むと、高志の姿はすっかりさおりそのものになっていた。 吼えることも忘れて、ぽかんとさおりの姿になった高志を見詰める子犬。 「どうだいゼリージュースの力は。素敵でしょう、哀れな子犬ちゃん」 その声はすっかり女性の、さおりの声に変わっていた。 「きゃん、きゃん」 「うるさいなあ、いくら吼えても何を言いたいのかわからないよ。 君は子犬なんだ、もう山口さおりのかわいいペットちゃんなの。誰一人君が本物の山口さおりだなんて思わないよ」 「く〜ん」 悲しそうに高志を見上げる子犬。 「……待てよ、もっと面白いことを思いついたぞ。ふふっ、ここに三浦の奴を呼び出してやるとするか。 あいつが僕のことを君じゃないって見破るか、それとも何の疑いもなく君だって思い込むのか。 君は大人しく聞いているんだな、ふふふ……」 裸の体にさおりの下着を付け、ドレッサーの中から選んだ黄色いサマードレスを着込んだ高志は 鏡の前で満足そうに笑うと、子犬になったさおりの首根っこを掴んでドレッサーの中に放り込んでしまった。 「ふふふ、三浦の奴が気がつくか、楽しみだ……わ」 「きゃん、きゃんきゃん」 子犬は、いや子犬になってしまったさおりは抱えられたまま吼え続けた。 「君は愛する彼と一緒になるんだ。一つの体にね」 そう言うと、さおりは子犬を中身を無くした祐二の抜け殻の中に放り込んだ。 膨らみ始める祐二の体。 そしてさおりは祐二に服を着せていく。 「か、かえして……」 「あらあら、声も男になっちゃって。すっかり祐二君になっちゃったね、さおりちゃん」 「あたしの体、かえしてよ」 「言ったでしょう、この体はもうあたしのものなんだって。あたしが山口さおりなのよ。 そしてあなたはあなたが愛してる恋人自身になるのよ。身も心もね」 そう言うと、さおりは祐二の体から出てきたゼリーを強引に祐二の姿へと化した本物のさおりに飲み込ませた。 「うぐっ、ごくっ、ごくっ」 「うふふ、これでいい。あなたは自分が山口さおりだったことなんか忘れて永遠に三浦祐二に成りきってしまうのよ。 そしてせいぜいあたしに尽くして頂戴。元の自分の姿をしたこのあたしにね」 やがてさおりを見詰める祐二の表情は、畏怖から戸惑いに変わっていく。 「あ、あれ? さおり、俺どうしたんだっけ、急に目まいがして」 「しばらく気を失ってたみたいよ。日射病? よっぽど暑かったのね。気をつけなくっちゃ」 「そ、そうか」 「大丈夫なの? 祐二、何かおかしなところはない?」 「ああ、もう大丈夫だよ、心配かけたな」 そう言って立ち上がると、祐二はぶるぶると頭を振った。 そんな祐二の様子を見て、さおりは気づかれないように、にやーっと嫌らしい笑いを浮かべた。 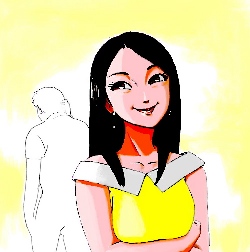 「ねえ祐二、あたしのこと愛してる?」 「は? お前、今更何を言ってるんだ」 「ねえ、どうなの?」 「愛してるさ。どこの誰よりも」 「嬉しい!」 ばっと祐二に抱きつくと、さおりは甘えるような上目遣いの表情で祐二を見上げた。 「ねえ祐二、今からプールに行かない?」 「え? 俺を呼び出したのって……」 「暑いから、祐二と一緒にプールに行きたいなって思ったの」 「よし、それじゃ行こうか」 「うん、とっておきのビキニがあるんだ。あたしのビキニ姿楽しみにしてて」 「とっておきのビキニ……」 「どうしたの祐二」 「いや、なんでもないさ。でも何か気になって」 「あたしの水着姿を想像したな。全くスケベなんだから。さあ行こう」 そう言うと、さおりは再び満足そうに笑いを浮かべた。 一方の祐二は「何か大切なことを忘れてる、忘れてはいけないことを」と頭の隅で思いながらも、それが何だったのか思い出すことができない。ただぼーっと水着や着替えをシースルーバッグに詰め込むさおりを見ていた。 「なにぼーっとしているの、祐二。さあ行きましょう」 「……あ、ああ」 1時間後、ホテルのプールを訪れた二人は、水着に着替えてプールサイドで戯れていた。 勿論その姿は誰が見ても、仲の良い恋人同士にしか見えない。 そして二人はフォトサービスの前でポーズを取っていた。 「どお? 祐二、このビキニ素敵でしょう?」 「ああ、よく似合うよ」 「ほんとにそう思う?」 「勿論さ」 「そお、ありがと」 (ふふっ、自分がさおりだったことはすっかり忘れちゃったみたいだね。 君のとっておきの水着、これももう僕のモノさ。そうさ、君の体だけじゃない、君の全てはもう僕のモノなんだ。 でも君はもういらない。 飽きちゃったら振ってあげるから、それまでせいぜい僕の恋人をやってくれよ。バイバイ、さおり) 「え? 何か言った?」 「ううん、何でもないよ、ほら祐二あっち見て」 PASHA!  (了) (2007年10月6日改訂版脱稿) 後書き ◎◎◎さんからいただいた2007年暑中見舞いを元にショートストーリーの「黒い夏」を書いたのですが、 その後◎◎◎さんから「黒い夏」を元にした数枚のイラストをいただきました。 それらのイラストを挿絵に使いつつ加筆修正したのが今回の【改訂版】です。 こういう作品作りができるなんてほんとにありがたく、そして嬉しいことです。 ◎◎◎さん、どうもありがとうございました! |