 |
||
西暦2057年。 進化した科学は、ついに神の領域へと到達した。 霊魂の発見とその証明。 それは、錬金術から分岐した科学が、再び錬金術に戻った時でもある。 脳とは別に人が持つもう一つの記憶媒体。そして、人格形成の核。 それを利用しようと幾多の企業が、軒並み霊魂の利用法を考えた。 西暦2063年。 アストラル社がついに、霊魂と肉体を分離する霊魂離脱装置を完成させる。 それは実験段階ながら、人の不死を可能としようとしていた。 実用化が始められた西暦2082年。 そして、今―― 1 『ボディ貸します』 頭上から聞こえるそんな声に、僕は空に浮いている宣伝用の飛行船を見上げた。 『生まれた時から決められたその身体。そんな自分では決められなかった自分の存在の枠を壊して、自分の選んだ新たな身体で魂をリフレッシュしてみませんか? かっこいい、可愛い。若いあの頃、見知らぬ大人の世界。 同性はもちろん。味わう事のない異性の身体。そして、禁断の動物の身体や遺伝子操作で作られたデミヒューマンに、その魂を転生させてみませんか? 新たなる発見を新たなる身体で。 今ならもれなく、新規入会者にはレンタル料金の割引券をプレゼントしますわ』 気が付けば僕は、街角で立ち止まり、飛行船の側面に付けられた大型のモニターに見入っていた。 レンタルボディ……か。 何気ない呟きが、口をついて出た。 頭脳明晰とまではいかないが、そこそこの知性を持つ頭。抜群とまではいかないが、自転車に乗るのに困らない程度の運動神経。顔も身体付きも人並にそこそこ。 あまりにも平凡すぎる僕は、悲しいことか21年の人生で女性にもてたことはない。 あっ、言っておくけど、恋人がいなかったわけじゃない。 これでも告白すれば、付き合ってくれた娘も中にはいた。 ただ、ものの二ヶ月もしない内に、『――って、何か面白味がなくてつまらない』と言い残し、僕の前から去っていく。 みんながみんな、同じ様なことを言うから、たぶんそれがもてない原因だと思うが、それが何なのか僕には分からず、直しようがなかった。 「かっこいい……か」 もし、平凡すぎてつまらない自分じゃない身体になった『自分』ならどうだろうか。少なくとも、今と違って突出した何かがあればもてるかもしれない。 「だけど、それじゃあ僕じゃないよな……」 不意に現実が脳裏を過ぎり、思いっ切り項垂れた。 ――何、あの人。突然にやにやしだしたと思ったら、いきなり地面によつんばいになって―― ――きっとあれよ。恋人にでもふられたのよ―― ――ちがうわよ。あの顔はもてそうにないから、恋人もいない自分に、気が触れたのよ―― 道を歩く女子高生達のささやき声が聞こえてきた。 まずい。 僕はあわててその場を立ち去った。 ▽ 今、僕は飛行船による宣伝を行っていたレンタルボディの店の前に立っていた。 今年の四月に入ってやっと政府の認可がおりたボディのレンタルサービスは、まだ一般的じゃないのか、30分ほど離れた位置から見ていたが、誰一人として利用者がいなかった。 「うーん。どうしようかな……」 辛うじて自動ドアのセンサーに反応しない位置で佇む。 利用者のプライベートを尊重するためかそれともただの飾りからか、曇りガラスのため中の様子が窺えれないことが、僕を勇み足にしていた。 どうも、こういうのは苦手なんだよな…… もし僕に、平然とこういうサービスを利用できる勇気があれば、もう少し女性にもてたかもしれない。 「ねぇ。入んないの?」 不意の声に、僕の心臓は大きく跳ねた。 恐る恐る振り返って見れば、ショートカットの女性が立っていた。 年の頃は二十歳前後。ジーンズ姿の少女はボーイッシュだが、かなり可愛い。 「あっ、別に僕は……もてないからかっこいい男になってみようかなと思っているんじゃなくて……、純粋な知的好奇心による……」 「何、訳の分からないこと言ってんのよ」 少女の冷ややかな言葉に、僕は無意識に見知らぬ女性に弁解している自分に気付いた。 頭に血が上り、顔が赤くなるの感じる僕の隣を、少女は何食わぬ顔で通り過ぎていった。 ――もう少し、本当の自分を出してみればどう?―― 微かに耳に届いた少女の声。慌てて振り返ると、丁度自動ドアが閉まるところだった。 「何なんだ……あの娘は?」 首を傾げてみるが、答えなどでない。 「あんなに可愛い娘でも、利用したりするんだ」 返却用の出入り口は別にあるため、今僕の前にある入り口は貸し出し専用のものである。 「まぁいいか。うだうだ考えていても仕方ない。入るとするか」 僕は、聞こえた少女の言葉を信じ、もう少し自分を出してみることにした。 「いらっしゃいませ」 ぐるりと軽く周りを見渡すと、そこには先程の少女の姿はなく、いるのは来店のあいさつを寄越してきた妖精のような容姿をした受付嬢が一人だけだった。 「ご入会ですか? 貸し出しですか?」 「入会を」 「ご入会はあちらの部屋にて窺っております」 言われた部屋に進むと、先程の受付嬢とまったく同じ容姿をした女性がいた。 「新規ご入会ですね。こちらの用紙に名前と住所、職業、年齢をご記入して下さい。あと、IDカードを提示して下さい」 「あっ、はい」 パスケースからIDカードを取り出して提示する。 案内がコンピュータにIDカードをかけている間に、僕は用紙に記入した。 「……様でよろしいですね。入会金プラス会費で2万3千円となります」 げっ、値段見るの忘れていた……。 「会費って、年会費? それとも永久なんですか?」 「ただ今サービス期間中ですので今入会の方のみ、永久会員扱いしております」 ホッとため息ついて、IDカードを支払機に差し込んで入会金を払い込む。 一人暮らしの貧乏大学生には、無駄に使える金はあまりない。 「今日はお借りになりますか?」 「はい」 「レンタルボディはどれにしますか?」 受付の片隅に設置してある投影装置から、ボディのカタログが投影された。 バストアップと全身図の3D映像。そして、その身体のデータが細かく記載されていた。 「あのぉー。レンタルの身体って、前に別の人が借りてるってことがありますよね」 「いえ、それはありませんわ。あらかじめ用意してあるのはDNAを操作して作り上げた一つの細胞だけです。それを、お客様のニーズにあわせて培養分裂させ、人の形をさせるのです」 僕の素朴な疑問に、案内嬢は、顔に張り付けたように浮かんでいた営業用スマイルを、一瞬本当におかしそうな笑みに変えてみせた。 たぶん、これがこの身体に乗り移っている本当の人の表情かも知れない。 「それで、どういった身体をお探しですか?」 「……かっこいい男性を」 「容姿端麗からマッチョまでかっこいい男性だけでもたくさんありますが」 …………。 「容姿端麗を」 少し間をおいて答えた。 初めてだから、あまり今の自分とかけ離れたのはまずいよな。いきなり突出しすぎた能力のある身体を選んでも、それを使いこなせるかどうかはわからない。 「年齢設定はどれくらいにしますか?」 「20才前後――」 「――――」 「――――」 「――――、――――」 「――――」 2、3の質問と共に次々と切り替わっていく映像。やがて、希望にあった数体のレンタルボディが選別表示された。 そこの中から、僕は一体の身体を選びだした。 身長は平均よりも少し高めで、細身の筋肉質。今流行りの顔立ちの身体だ。 「お客様、レンタルボディのコード表示位置は何処にしますか?」 「コード?」 「レンタルボディには、それぞれのレンタル会社のデータ及びお客様のデータをバーコード化して身体の一部に記しておく決まりがあるんです」 そう言って彼女は髪の毛を掻き上げ、僕にうなじを見せてきた。 髪の毛に隠れて見えなかった白く細い首後ろには、場違いなバーコード入れ墨のように記されていた。 「大抵の方はなるべく目立たない場所――女性でしたら太股の内側、男性でしたらお尻などが多いですね。ただ、中には、その身体がレンタルされたモノだと誇示するように、腕や手の甲、顔に記す人もいます」 少し考えた末、僕は右肩にそれを記してもらうことにした。そこなら、服で隠すこともできるし、また誇示することも可能だからだ。 「基本性格等はどうしますか?」 「基本性格? 何ですか、それ?」 「新しい身体に宿るのですから、性格をも変えたいと希望するお客様のために用意いたしたものです。例えば、異性の身体に宿って元の性格のままだと日常生活にご不都合がありますから。勿論、基本性格設定無しをご希望でしたらそのようにいたしますが」 「別に異性に宿るわけじゃないしな……どういったのが用意されているですか?」 「活発、勇猛……鬼畜や粗暴などがありますが」 僕がもてないのって、性格が関係してるかも知れないからな…… 先程の少女の一言が脳裏を過ぎった。 うん。どうせなら性格も変えるか。その方が面白そうだし。 「明朗活発で頼みます」 「分かりました。では、こちらへ」 手続きと説明を終えると、僕は奥の装置が置かれた部屋へと案内され、部屋の中央に縦に設置された二本の円筒系の筒の一本に入るように言われた。 「あっ、そう言えば。レンタルボディを使っている間、僕の身体はどうなるんですか?」 「お客様のお身体は、霊魂が分離した後、データ変換を行い――」 「データ変換?」 聞き慣れない言葉に僕は筒の中で首を傾げた。 「物質転送装置の理論を元に開発された最新鋭の技術の一つで、対象物質をデジタル化するものです。当社ではその技術を利用し、お客様のお身体をデジタルデータに変換し、当社のデータバンクにて返却の時まで大事にお預かりいたしております」 にこっとやんわりとした微笑みを浮かべ、案内嬢はさらに言葉を付け加えた。 「もし間違っても、身体を返さずに逃げようなんて思わないで下さいまし。その様な場合は、お客様のお身体をこちらで好きなようにさせて頂きますので」 …………。 顔は笑っているんだけど、目がまじだよ…… 「大丈夫ですよ。僕は自分の身体が嫌いじゃないんですから」 答えてみるが、頬がひきつって上手いこと笑えない。 「クスッ、冗談ですわ。レンタルボディの頭の方には、犯罪目的や法に引っかかる事をしようとすると、ストッパーが働くようにインストールされていますから」 案内嬢がスイッチを入れると、筒の中で僕は意識を闇の中に落とした。 ▽ 筒の中で僕は目を覚ました。ただし、あまり気持ちのいい目覚めではない。 ちょうど、微睡みの中から強引に現実世界に引き戻された感覚に近い。 焦点が定まり輪郭がハッキリしてくる視界。そして、肌には排出されたばかりの培養液の残りが濡らしているのを感じた。 「手……あるよな」 目の前に手をかざしてみた。 培養液で濡れている手は、やけに白く細い腕に見えた。 「頼んだ身体よりも、かなり細いような……? ディスプレイで見るのと、実際の目で見るのとでは違いがあるのかしら……」 傾げた首から、肩に髪の毛が触れた。 「…………」 確か……ここまで髪の長いボディを選んだ記憶はないはずだけど…… 髪をよく見ようと視線を落とした僕は、自分の胸を見て絶句した。 「?!??!!!!?」 そこには形の整った二つの双丘があった。 「胸……」 そっと触れてみると、柔らかくも暖かい感触が伝わってくる。 呆然といじくっていると、指先の触れた乳首からえも知れぬ感覚が走った。 「――ぁっはん」 味わったことのない感覚に、無意識に声が出た。 女性の声!? そこで始めて、先ほどから発している自分の声が、男性のものよりも高い事に気が付いた。 「女性の身体……」 現実を直視した時、僕の入っていた装置の前に、レンタル会社のスタッフが数人やってきた。 「お客様! 緊急自体が発生しました!!」 ▽ 「申し訳ございません」 案内の娘が用意してくれた服を着込んだ僕の前で頭を下げるのは、この店の店長だと言う。 何やら先程から平謝りに頭を下げてくれるが、その言葉は僕の耳を素通りしていた。 ズボンか……せめてロングのスカートは無かったのか…… 今の僕は、黒のミニスカートに黒のノースリーブのシャツ、それらと同色の半袖のジャケットという姿であった。 勿論僕の趣味ではなく、案内嬢が用意してくれた物である。 何でも、全ての体型にあった服は用意されているのだが、たまたまこの身体のサイズに合うのが、それ一着しかなかったそうなんだけど…… ハッキリ言って、ミニスカートってヤツは恥ずかしい。 膝上の裾のため、まるで足に何も履いていない気がする。半ズボンとでも思えればいいのだが、股がスースーしてとても半ズボンとは考えにくい。自分本来の身体じゃないから羞恥心なんて働かないと思っていたが、ついつい膝を揃えて椅子に座っていた。 …………。 はて? 馴れない少女――鏡を見ていないからハッキリとは言えないが、どうも今の自分の身体の年齢は女子高生ぐらいだと思う――の身体に無理矢理入れられたためか、何かがおかしい。 微妙に感じる違和感。 そんなことを考えている僕の前では、謝っていた店長が他の会員の元へと謝りに向かい(僕と同時期に身体を借りた数人の会員にも同じことが起きていると言う)、入れ替わるようにやってきた技術者が今回の事故について色々と専門的な説明をしてくれた。 「外部ネットから進入したウイルスがメインシステムに感染し、システムに狂いが生じ……」 漠然とは分かるが、深い意味は分からない。 ただ、確実に分かることと言えば―― 「つまり、そちら様のミスで、僕は……様!?」 普段の僕なら、いくら当たり障りのない性格をしているとはいっても、ミスを犯した相手に様などといった敬称を付けるはずもない。 「何か、変……です」 です――だって!? 分かった。 僕は分かった。自分が先程から感じている違和感が…… 心で思う考えと、頭を通して出た身体から出る雰囲気に食い違いがあったのだ。 「……もしかして、基本性格が設定されているんですか?」 「いえ、それはされておりません」 「なら、何故、今の僕はこんな風なんですか?」 「それは、C−203Kの身体には基本性格は設定されていませんが――」 C−203Kって言うのは、この身体のシリアルナンバー何だろう。案内嬢の手助けで今の服を着せられた時に、太股の内側に記載されたバーコードの一部にそのナンバーが記されていた。 「基本的性質がインストールされており、その性質が表に出ているためです」 「性質? 性格とは違うんですか?」」 「性質設定とは、性格のさらに奥に存在する無意識領域の設定のことです。例えば、性格が無骨で性質が優しさだと、ぶっきらぼうながらついつい陰で人を助ける――みたいなものです。 普通でしたら、性質設定は行わないのですが、C−203Kの身体を借りる予定でした本来のお客様のご要望だったんです」 言われてみれば、いくらシステムにウイルスが侵入し誤作動を起こしたとはいえ、用意もされていない身体になっているわけはないか。 しかし…… 「いったい、どんな身体に入れられたんですか。この身体のデータを見せて下さい」 2D映像が僕の目の前に投影された。 白い肌、黒い髪。そして、鳶色の瞳。全体的に華奢な美少女の映像が映し出された。 服を着せられた時は、更衣室などに行かず装置の影で案内の娘達に着せられたので、今の自分の顔を見るのはこれが始めてであった。 写真の隣にびっしりと記されているデータ。 年齢欄を見れば、予想通り18才前後となっていた。 そして、何より僕を狼狽させたのが、問題の基本的性質であった。 「従順で大人しい……」 その性質に、僕の目の前は暗くなりかけた。 これじゃあまるで、奴隷向けな性質じゃないか。 いったい、この身体を指定した奴は何考えているんだ? 「データは分かりましたが、いつまでこの身体でいなければならないんですか? 今すぐ、僕の本当の身体に戻していただけるのでしたら、別に訴えたりとかはしませんけど……」 「それがあいにく、一度、幽体離脱をおこなうと、装置に耐えられるだけの霊力が回復するまでの間はおこなえないのです。普通でしたら半日もすれば回復するんですが……お客様は、こちらで調べた結果、間違った身体に入ったために上手くシンクロができず、霊力が必要以上に消耗しておりまして」 「それで……」 「霊力の回復には、だいたい一週間はかかります」 ▽ それから後のことはあまり覚えていなかった。 ただ、裁判沙汰にしない代わりに、VIP待遇(半永久的にただ同然の金額でボディをレンタルできる資格)の会員の権利と、多額の謝罪金。そして、霊力が回復するまでの一週間の住む場所の提供を約束して貰った。 今となって、これが犬猫の身体じゃなかったことだけが幸いと思うしかなかった。 2 レンタル屋に提供された住む場所への道順を地図で確かめながら、僕は大通りを避けて路地裏を歩いていた。 何故路地裏を歩いているかって? それは恥ずかしかったからだ。 少女の身体だというのは別にいい。ただ、その身体があまりにも美少女すぎるのか、周りの人達(主に男性)のまとわりつくような視線が嫌だったのと、ミニスカートのため股がスースーして人前を歩く気にはなれなかった。 それに、この裏路地に入る前に一度ナンパされかけた。心では強く断ろうと思っても、刷り込まれている『従順で大人しい』性質が邪魔し、無理矢理付き合わせられそうになった。 幸い、偶然にもナンパ男の付き合っている彼女が現れたため、その場は事なきをえたのだが…… ハッキリ言って、男に言い寄られてゾーッとした。 しかも、従順な性質を持つ今の僕は、もし関係を迫られでもしたら何処まで自分の意志を貫き通せれるのか分かったものじゃない。 「ふぅー。ずいぶんと気弱な考えしか浮かばないな……」 口から出るのは愁いを帯びたため息だけだった。 とぼとぼと路地裏を歩く僕の足――が止まった。 狭い路地の先に、男性が数人にたむろっていたのだ。年の頃は高校生ぐらいだが、雰囲気からいって真っ当な学生には見られない。 やばい感じがするな…… 嫌な予感を胸に抱きながら、僕は彼らを無視するように先を急いだ。 何もなく、彼らの横をすり抜けた―― 「きゃぁっ!」 思わず飛び出た悲鳴が女の子のそれに変わっていたことに、その時の僕には気付くゆとりがなかった。 「いきなり、何するんです」 背後から僕の腕を掴んできた男が一人。 僕はそいつを睨み付けたのだが、如何せん、視線に迫力がない。いや、それ以上に目に涙なんかが浮かんでいるのを感じ取った。 「よう、ねえちゃん。俺達と遊ばない♪」 掴まれた腕を何とか振り解こうと力を込めるが、今の少女の力では男の力にはかなうわけもなく、路地裏の更に人気のない袋小路へと引きずり込まれた。 何度声を上げて助けを呼ぼうかと思ったが、刷り込まれた大人しい性質が邪魔をするのか、それともただ単純に恐怖に声がでないのか、口から出るのは声にもならない息だけであった。 ――――ッ!? 突然の感触に、思考が一瞬止まった。 胸を揉み扱かれたのだ。 本来の僕の男の身体では感じることのない不思議な感覚。快感などあるはずもない。あるのは、男に犯されるという恐怖に彩られた痛みだけ。 「や、やめて……」 「そう脅えるなよ。今、気持ちよくなる薬をやるから」 男が僕の顎を掴み、震える唇をこじ開け、妖しげなカプセルを押し込んできた。多分、性感体を刺激するドラッグの一種だと思うけど…… 「吐かずに飲み込めよ」 舌で何とか押し止めていたカプセルだったが、男の放った命令に従って、無情にも僕はそれを飲み込んだ。 「後数分もすれば、自分から俺達を欲しくなる」 吐き出そうとしてみるが、一度飲み込んだカプセルは喉の上に上がってくることはなかった。 「おい、こいつバーコードがプリントされてるぜ」  まくり上げたスカートの中に顔を突っ込んでいた男の一人が、内股に記されているバーコードを見つけた。 「それって確かレンタルボディーの証だろ。テレビで見たことある」 「じゃあ、こいつって、本当は別の人間なのか?」 「僕は男だ。男を犯すなんて気持ち悪いだろ」 多少なりとも躊躇ってくれないものかと思って言ってみたが、 「だけど、身体は女なんだろ?」 その台詞に、僕の顔から血の気がひいた。 それに伴って、身体の奥底が熱くなってきたのを感じた。僕の身体に触れてくる男達の指先に、感じ始めてきているのだ。たぶん、さっき飲まされた薬が効いてきたのだろう……けど、まずすぎる! 僕は最後の力を振り絞るようにして、迫ってくる男達の手から逃れようとした。 ――――。 いつの間にか下げられたパンツ――この場合、ショーツか――が足首に絡み付き、僕は思いっ切り前に倒れた。 頭を上げて振り返ると、男達が嘲笑と共ににじり寄ってくる。 ハッキリ言って、男のスケベそうな笑みがここまで不気味だとは、僕は初めて知った。 そして、男達の手が再度、僕に延ばされた時―― 「――あんた達! 何してるのよ!!」 そんな叫びを遠くに聞きながら、僕の意識は闇へと落ちた。 ▽ カーテンの隙間から射し込む陽射しに、僕は目を覚ました。 「――天井」 ぼぉーっと辺りを見渡す僕の目に最初に入ったのは見知らぬ天井だった。そして、何も知らない部屋。 多分マンションかアパートの一室だと思うけど……ハッキリしているのは、その部屋から生活感が感じられないことだった。これで段ボール箱が積んであれば、引っ越ししてきたばかりか、引っ越し前夜の部屋とでも思っただろうけど。 「?」 何故、僕がここにいるのか思い出せない。どうも、記憶があやふやだ。 「ここは……」 上半身を起こすさい、頬に触れた髪――そして、見下げた身体の華奢な作りに、自分が女性の身体に間違って乗り移っていることを思い出した。 一つ認識すれば、後は簡単だった。 だがそれも、襲われてる途中に気を失う寸前までしか覚えていない。 まさか、既に犯された後とか…… 自分の今の姿を見てみると、レンタル屋で借りてきた服は無く――案内嬢に付けて貰ったブラジャーまでも外されている――ただ、ショーツと一枚のTシャツを着込んでいた。 服が着替えさせられているってことは……やっぱり犯されたのか!? 最悪の状況が脳裏を過ぎった――が、変だ。 僕を襲おうとした連中が、こんな部屋に連れてくるはずがない。もしあったとしても、それは縛られるなりの監禁を受けているはずだ。 普通にベットに寝かしつけるとは想像しがたい。 考えれば考えるほど自分の現状が分からず、更にいっそう頭を悩ます。 「あっ、気付いたわね」 部屋の奥――正確に言えば部屋の入り口の方角から声が聞こえた。 造りからして、キッチンにでも誰かいるのだろう。 「催淫剤の効き目が切れるまでは寝かせておいた方がいいと思って、いままで寝かせておいたのよ」 お盆の上に二つのティーカップを載せ、一人の男性がやってきた。身長は高く、細身の身体。ただ、必要な筋肉はしっかりと付いている。そして、創られたような整った顔立ちの男。年は大体二十歳ぐらいだろう。 「誰? あなた――」 ベットの上で身体を堅くする僕に、 「貞操の危機から助けてやった恩人にそれって無いと思うけど」 苦笑と共に、そいつは持っていたティーカップを差し出してきた。 「これでも飲んで少し落ち着きなさい。レイプされそうになって、気持ちが高まっているでしょ」 黙ってカップを受け取る。 立ち上る湯気の臭いからして、紅茶なのが分かる。 「助けてくれたって、あの高校生達を倒したんですか?」 「殺陣を学んでいるからね」 そう言いながら青年は、僕のいるベットに腰掛けてきた。 「アレくらいの数なら、上手く立ち回れば何ってことないわよ」 ――わよ? えっ? 女言葉? まさか……おかま? そんなことを考えながら、僕は青年が紅茶を飲む様を見つめていた。 その動作、上品とは言い難いが、男性の飲み方にしては何処か繊細さがある――あれ? 僕の顔に浮かんだ怪訝な表情を読み取ったのか、青年はやんわりとした笑みを浮かべた。 その笑顔、 「やっと気付いたわね」 身体は男だが、僕には至極コケティッシュなものに見えた。 「この身体は本当なら、貴方が借りる物だったんでしょ。今の貴女の身体が私が借りる予定だったように」 青年は着ているTシャツの右袖をまくり上げる。 露になった筋肉質の右肩には、僕が指定したとおりにバーコードが記されていた。 確かに『彼』は、本来なら僕がなるべく人物だった。 それから『彼』は色々と教えてくれた。 『彼』の正体は、僕がレンタル屋に入る前に出会った少女で、希望とは別の身体に入れられた彼女は、僕の場合と同じようにレンタル屋との示談が付き、僕から少し遅れてレンタル屋を出たそうだ。 そして、同じようにレンタル屋が用意してくれた部屋に向かう途中、偶然襲われかけている僕を見つけ、助けてくれた。 「――って、ことでレンタル屋が用意してくれた部屋まで運んで来たのよ」 今現在いる部屋は、彼女のために用意されたもので、僕の部屋は隣だと教えてくれた。 「それは、ありがとうございます」 素直に頭を下げると、彼女は困ったような笑みを見せた。 「いいって、いいって。あなたが無抵抗のまま襲われた原因の一つに、あたしが性質設定をおこなっていたのがあるんだからさ。 あっ、でも、あなたもこの身体に性格設定を施しているからあいこよね」 …………。 どうも男の姿で少女の言葉遣いされると……おかまにしか見えない。 「どうして従順でおとなしいなんて性質設定を希望したんですか? こんなの百害あって一理無しじゃない」 「あっ、それ。それについて、あなたに頼みたいことがあるのよ」 「頼み?」 訝る僕を無視し、『彼』は頼みを口にした。 「あなたに、あたし達の舞台に出てほしいのよ」 「舞台って演劇の舞台?」 「そう、それ。今のあなたに施してある性質は、実は主役を演じる上で必要なモノなの。本当は別の娘が演じるはずだったんだけど。その娘、身内の不幸があって、実家に帰っちゃったのよ。おかげで代役を用意しなければならなくなったんだけど……残っている仲間はみんなアクが強くてね、主役を演じれる人材がなかったの。 それで、誰かが提案したのよ。雰囲気を出せないのなら、レンタルで役の性質設定を施した身体を借りてやればいいって。それで、くじ引きであたしが『その身体』を借りる羽目になったの。 本番も六日後に迫っていて、別の身体に入るにしても、霊力の回復が間に合わないのよ。だから、あなたに出てもらいたいの。どうせ、その身体でいる間は誰とも知人とは連絡取れないでしょ」 …………。 確かに、友人とは連絡は取れないか。正直なことを話したとしても、あいつらのことだ、何悪戯されるか分かったものじゃない。 「言いたいことは分かりましたけど。僕に演劇なんて無理ですよ。まして主役だなんて……」 助けられた恩があり、設定されている大人しい性質のため、僕は強く断れなかった。 「大丈夫だってば。監督兼脚本、演出担当のあたし――木幡ケイが責任を持って主役を張れるように鍛えてみせるから。 ね♪」 ね――ってね。男の姿でウインクされても嬉しくはないんだけど…… 何も応えずにいると、ケイはずいっと顔を近づけてきた。何処か悪戯っ子な微笑みが浮かんでいる。 ――ドキッ。 あまりにも迫ってきたケイの顔に、一瞬胸の奥で何かが跳ねた気がした。 何なんだ、今のは? 自分の身体に感じた奇妙な感覚に戸惑っている僕に、ケイは一言言った。 それは、僕の意志の全てを無効にするだけの力のある言葉。 「やってくれるよね」 「……はい」 従順な性質に支配された僕の口から出たのは、承諾の返事。あくまで逆らおうとしている僕の意志は、頭を垂れさせ、視線を落とすことしかできなかった。 ▽ 舞台に立つことを約束させられた僕は、早速とケイさんの所属している演劇のサークルへと連れ出されることとなった――のだが、レンタル屋で借りてきた服は襲われた際に汚れ洗濯中で(今着ているTシャツは、ここへ運ばれる途中でケイさんが買ってきた代物だそうだ)、ケイさんに頼んで服を買いに行って来て貰った(今の体のサイズは事細かなデータが存在し、僕本人が行かなくても服は選べた)んだけど、 「ちょっと、ケイさん」 ケイの買ってきてくれた服を見て、僕は大きく項垂れた。 彼女もまたレンタル屋から多額の賠償金を貰っているらしく、僕の好みが分からないと言う理由で、レンタル屋で借りたモノよりも裾の短いきわどいミニから足首まで隠れるロングまで多種多様なスカートを買ってきてくれたのはいいんだけど…… 「僕はズボンを頼んだはずだけど……どうしてスカートしかないわけ?」 しかも、上は上でボディラインを際立たせるような服が多い。 「だって、あなたには舞台当日までに完璧な女性を演じて貰いたいんだから、まずは外面から女性らしくなって貰おうと思って」 なるほど。彼女の考えはだいたい分かってきた。 いくら性質設定された女性の身体でいようと性格設定が施されていない身体じゃ、男の僕が宿る以上内面から出る雰囲気が男のそれである。まして、本番までたったの六日間しかないため、演劇素人の僕じゃとても稽古じゃ隠しきれないと危惧しているんだ。 それをケイは、僕の生活全てを女性のそれにし、強引に隠す気でいる。 「たったの六日間だから、お願い。女性になって」 目の前で両手を併せてみせるケイ。 ただ、男の身体でしなを作られても気持ちのいいものじゃない。 「――お願いって、命令はしないのですか?」 そう。命令だ。 先程みたく命令されれば、この身体でいる以上命令を受けてしまう。 「それは駄目よ。あなたには、舞台当日までに完璧な女性を演じてもらうんだから。そのためには、あなたの意志を無視して命令で女物の服を着させても仕方ないから。あなたの意志でそれに着替えてもらわないと、心の底から女の子を演じてもらえないじゃない」 ケイの考えには納得できるが、いざ着てくれと言われても着るには抵抗がある。 躊躇い続ける僕に、ケイは最後通牒を投げかけてきた。 「どうしても着たくないって言うなら、その姿のまま街に連れ出して、男性の視線を目一杯浴びさせて羞恥心を扇がせて精神の女性化をはかるわよ」 「うっ……」 僕はしぶしぶと、ケイの用意してきた服に着替えることになった。 選んだ服を脇に置き、ベットの上でTシャツを脱ぎにかかる。 ――――。 「どうしたの? 着替えないの?」 「バスルームで着替えてくる」 僕は服を片手にケイの前を通り過ぎた。 「ちょっと、別にあたしの視線なんて気にしなくてもいいじゃない」 「気になるものは気になるの」 別に今のケイが男性だからってわけでもない。ただ、人に今の自分の姿を見られるのが酷く恥ずかしく感じられたのだ。 「…………」 トイレに洗面台の併設のそこには、真正面に鏡があり、否応なく今の自分が女であることを意識させてくる。 「はぁー」 ため息をつくと、僕は着ていたTシャツを脱いだ。 豊満ではないがそれとなく整った形の胸が鏡に映し出される。 うーん。よくよく考えれば、こういう風に自分の姿を見たのは今が初めてなんだっけ。 しばらく鏡とにらめっこした後、僕は一つのことに気が付いた。 「そう言えば、ブラジャー持ってきていなかった……」 ケイの用意してくれた服の中には下着も数点あったが、それを持ってくるのをすっかりと忘れていた。 今更取りに行くのも何だし、まして付け方も分からない代物。 別に無くてもいいか。 そう思って、ノースリーブの白いシャツを着てみた。 「…………」 クッキリと形が現れる乳首に、僕は脱いだTシャツに手をかけた。 ブラジャー……取ってくるか。 仕方なく、Tシャツを着直して外に出ると、不遜な笑みを浮かべたケイが立っていた。 「はい、忘れ物。付け方分からないなら、手伝って上げるわよ」 「いいです」 僕はブラジャーだけを受け取り、扉を閉めた。 格闘するようにブラジャーを身に付けると、僕は再度服を手に取った。 着替えながら、まだ扉の向こうにいると思われるケイに問いかけた。 「いったい、どんな劇をやるんです? こんな危なっかしい性質設定を施さなければならない主役って」 この身体に宿った時から考えている最大の疑問だ。 どう考えても召使いのような性質が主役を張れるとは思えない。 「シンデレラよ、シンデレラ。知ってるでしょ」 シンデレラ……ね。それなら納得ができるか。 確かに、継母達に虐められるシンデレラの性質にはもってこいか。 「もっとも、かなりシナリオをいじっているけどね」 「どんな風にいじってあるんです?」 「後でシナリオ見せてあげるから、早く着替えてよ。稽古の時間まで間がないんだから」 ケイに急き立てられ、僕はロングスカートを履いた。 「これって……」 ケイの用意した中で一番落ち着いた露出部分の少ないモノを選んだのだけど……まさかスカートの側面にチャイナドレス並の深いスリットが入っていたとは。 裂け目から見えるスラリと白い脚。 今更服を選び直す気にはならなかった僕は、そのままバスルームを後にした。 3 連れてこられた目的地の門の前に、僕の足は止まった。 麗淑女子短期大学―― 「女子大?」 「あれ? 言ってなかったかな。あたしの入っている演劇のサークルって大学のよ」 ケイは僕を先導するように、目的地である演劇部の部室へと案内してくれた。 突然部室に入ってきた男性――ケイのことだが――に、ざわめき出す数人の女子大生。 集まっている演劇部員にケイが自分の正体を明かし、順を追って説明するに当たって、部員達の注目はケイから僕へと映ってきた。 「――っと言うことで、彼――彼女があたしの代わりにシンデレラの役をやってくれるそうよ」 ケイに肘で突っつかれて、僕はペコリと頭を下げた。 余程の人材不足なのか、部外者である僕の参入を彼女達は手放しで喜んでくれた。 「しっかし、ケイが男とはね……」 「不幸中の幸いですよね、部長」 「不幸中の幸い?」 部員達の会話に、ケイが口元に人差し指を添えて小首を傾げた。 少女姿での仕草なら可愛げもあるんだけど、二十歳の青年にやられると気持ち悪い。 「りっちゃんが舞台の日に結婚式が入ったんだって」 険しい顔でケイが視線を向けた女性が、そのりっちゃんなんだろう。 身長は今のケイと比べても遜色のない、女性にしては長身の分類に入る背の高いショートカットの女性だ。 聞けば、何でも王子様の役をやるひとだったらしい。 「結婚式って、欠席できないの?」 「それが、従姉妹で何かと世話になっている人だから、出ないわけにもいかなくて……ごめん」 と頭を下げるりっちゃん。 「それで、誰かに代役として、またレンタルボディを借りに行ってきて貰おうかとも考えていたんだけど……ケイがその姿なら問題無いわね」 「あたしにやれってこと……ね」 「そっ。シナリオと演出、監督まで兼ねているあんたなら、セリフ全部頭に入っているでしょ」 「まぁね」 不敵な笑みを浮かべて頷くケイ。 「それなら、早速稽古に入るわよ。練習時間も残り少ない上に、急の代役、しかも一人は女性初経験の男性ときたから、みんなしっかりフォローしてあげてよ」 ケイの号令に、部員達は一斉に動き出した。 一人、取り残されるようにその場に立ち尽くしていると、衣装担当の小柄の女性に衣装合わせしたいと部室の一部を仕切って作られた衣装部屋へと連れて行かれた。 「…………」 講堂のステージの上に作られた舞台に、僕の思考は止まった。 いや、既にこの衣装に着替えさせられた時に止まっていたのかもしれない。 「あっ、やっと来たな」 さわやかな笑顔で講堂に入ってきた僕を出迎えたのは、ケイだった。 「遅いぞ。俺達には無駄な時間は無いんだから」 「?」 「何だよ?」 「言葉遣い……」 そう、ケイの言葉遣いが男のモノに変わっていたのだ。 「ああ、これ。男性の役を演じるからには、言葉遣いを変えないとまずいだろ」 「まぁ、そうだけど……」 今までの女言葉よりかはその姿に合っている。 「それより、この姿っていったい何なんです」 僕は自分の着ている服を指さして、ケイに問いつめた。 着せられた衣装は、とてもシンデレラを連想させるようなものではない――女子大生が卒業式に着るような羽織袴だった。 シンデレラって言うから、メイドの着るような服か、きらびやかなドレスでも着せられるかと思いきやのこれである。 身体のラインがハッキリ出る洋服とは違って胸の膨らみとかは目立たないのはいいが……この姿はこの姿で、女性専門――しかも、普通ではお目にかかれない限られた一部の女性――の服装であるから、気恥ずかしさは変わらない。いや、意表を突かれた分だけ、恥ずかしくもある。 「かなりシナリオをいじると言ったはずだけど……」 腰に手を当て、困ったようにひと息つくケイ。 「俺達が演じるのは、大正浪漫風シンデレラなんだよ。 意地悪な女学校の先生やクラスメイトに虐められるつばめ――シンデレラの名前だけど――と若き海軍将校のラブロマンスなんだ」 「それで大正時代の女学生の姿……」 自分の履いている袴を見下ろして呟いた僕の言葉を勘違いしたのか、ケイの説明は更に続いた。 「あっ、大丈夫だよ。魔法使いのおばあさんは出ないけど、ちゃんとドレスは用意するから。何なら、がレスの靴も用意するけど」 「この上ドレスまで着るわけ……」 やる気を奮い立たせようと言った言葉なのかは分からないが、ケイの意図とは違って、僕の心はかえって憂鬱になっていった。 「シナリオ見せて下さい」 ホッチキスで綴じられたコピー用紙を手渡された。 見れば表紙にでかく『愛、奮える心』と記されている。そのタイトルからでは、どんな物語か予想もつかない。 流れを読み取るかのように、僕はパラパラと目を通していく。 大まかな物語の筋はこうだった。 時は大正―― 所は海軍軍港のある都市―― 軍国主義を唱える陸軍に逆らって、軍縮を叫ぶ大臣――つばめの父。その煽りを食って、親に軍人を持つ同級生から様々な虐めに遭うつばめ。 彼女は健気にもそれを誰にも言わず、独り必死に耐え続ける。 それは、ある雪の日のことだった。 つばめは一人の海軍青年将校と出会う。『覇』を唱える軍隊で、『和』を重んじる青年将校。 その時の二人の出会いは、袖摺りあうような些細なものだった。 陸軍中将が画策した罠にはまり、非業の死を遂げるつばめの父。 幸い、僅かな蓄えがあり、卒業するまで女学校には通えるつばめだったが、彼女に対する虐めはさらにエスカレートしていく。 そんな絶望のどん底でつばめは自殺を決意する。浴室で手首を切るつばめ。朦朧とする意識の中、彼女は助けに現れた青年将校の後ろ姿を見た。名を告げず、顔も見せずにつばめを助ける青年将校。彼は、つばめの父である大臣と、海軍の大将の命を受けて陸軍の様子を見張っており、その計略によって殺された大臣の代わりにつばめの行く末を見守っていたのだ。 つばめが意識を取り戻した時、手首には包帯が巻かれ、枕元には青年将校の残した手紙が置いてあった。 そして、つばめを助ける時にでも落としたのだろう、階級章が落ちていた。 どこがシンデレラなんだ……? 読めば読むほど、どういう風にシンデレラのシナリオをいじったのかは分からなくなっていく。 更に、僕は頁をめくった。 絶望の淵から立ち直るつばめ。 微かに記憶に残る青年将校に心を焦がしながらも、彼女は単身で陸軍の企み(軍国主義を目指すクーデター)を調べ始めた。そんな折り、父の書斎から陸軍の企みを記した報告書を見つることに。 それを片手に、天皇が開催する宮中晩餐会に忍び込むつばめ。そこには、政財界のトップに軍の将軍達も集まっていた。そこで彼女はそれを公表する気でいた。 だが、それをいち早く察した陸軍の邪魔に合う。それを救ったのが、一人の青年将校だった。 つばめの代わりに凶弾にあう青年将校。階級章から彼が自分を見守ってくれた青年将校だということを知るつばめ。 青年将校のおかげで、陸軍の企みを全て公にし未然に防ぐことはできたが、彼は今にも息絶えようとしていた。 今まさに死が訪れようとした彼の口に、涙を流しながらつばめは自分の口をあてた―― 「キス!?」 自分の口から出た素っ頓狂な叫びに、周りで芝居の準備をしていた部員達が一斉に振り返った。 そんな彼女たちの視線など気にせず、僕は間近にいたケイに問いつめた。 「ケイさん。このラストシーンって……」 「ああ、それ。やっぱり、死が二人を分かつ時はそれなりにロマンチックじゃないと、観客受けしないし……何か問題でも?」 「ロマンチックなのはいいけど、僕は嫌だよ。男とキスなんて――ッ!?」 いきなり顎を持ち上げられ、軽く口付けされた。 「なっ、なっ、なっ、なっ、何するんだよ!?」 酷く自分が狼狽しているのが分かるが、今はそれどころではない。 「これで、もうキスシーンも平気だろ」 ニコッと健やかな笑顔を浮かべるケイに、僕は頭を殴ってやろうかと考えたが、おとなしさを宿命付けられた身体は僕の意志を反映することはなかった。ただ、ただ、顔を真っ赤にするのみ。 これじゃあ、本当にうぶな少女の反応だよ。 心の中の一部が、酷く冷静に自分を見ていたことに、気付いた。 「だいたい、これのどこがシンデレラなんです?」 「うーん。始めはシンデレラの和風を目指してシナリオ書いていたんだけど、いつしかそんな風に変わってしまってね。俺にもよく分からないんだよ」 そう言って、軽く肩を竦めてみせたケイ。 ▽ それから四日間、僕はケイの特訓を受けた。 住んでいるところ――レンタル屋に用意された部屋のことだけど――が隣り同士ということもあって、寝る時間全てをお芝居の特訓に費やされていた。 幸い、真っ新な脳味噌は、水を吸い込む綿の如くセリフを覚えていくのだけど……いまだ女性の身体に馴染めきれない僕のセリフは女性のモノになっていないとケイは言う。当たり前である。精神まで少女になったつもりは無い。 そんな僕とは逆に、演劇で男性の役を演じたこともあるケイにとって、男の身体でいることにはさほど違和感がなかったようで、言葉遣いも男性のものに変えた今、時折浮かべるコケティッシュな悪戯っ子の笑み――どうも、彼女の癖らしい――を除けば、完璧な男である。 舞台の上で稽古をしているケイの姿を見ながら、僕は片隅で一息ついていた。 僕の隣では、衣装係の娘と小道具の娘が二人、いた。 「先輩。ケイ先輩って、完璧に青年将校を演じていますね」 「演じているんじゃないって。あの娘ってば、どんな役でも手を抜かず、精一杯頑張るからね。完璧になりきってるのよ。自分の理想としている役柄に」 二人で話していたかと思うと、不意に衣装係の娘が僕の方を見つめてきた。 「その割には、キミはいっこうにつばめと同化しないわね」 ケイと同じキャリアを持っているのか、彼女はケイと同じ印象を受けていたようだ。 しばし、僕と見つめ合い、そして彼女は舞台のケイに呼びかけた。 「ねぇ、ケイ。ドレスの方ができたんだけど、この娘に着せてもいい?」 この娘ってね…… 実年齢は四大の四年生である僕の方が上なんだけど、身体の年齢が17才前後のためか、部員達は時折僕のことを子供扱いする。 「ドレス? ああ、いいぜ」 すっかり板に付いてしまったケイの男言葉。ただ、浮かべたコケティッシュな笑顔は、僕に彼女が女性なのを思い起こさせた。 ▽ 衣装係の娘と小道具担当の娘に引っ張られるように、講堂から部室の衣装室へと連れてこられた。ここに訪れたのは、初日に羽織袴を着せられて以来の二度目だ(あれ以来、衣装は使わず、舞台稽古をしていた) 衣装係の娘が置くから一着のドレスを取り出してきた。 大正浪漫の言葉に恥ずかしくない少し古く、そして新しいデザインの薄桃色のドレス。 「さぁ、これに着替えるから、服脱ぎましょ」 「えっ!?」 あっと言う間に、僕は裸にされドレスを着させられた。 「どこか苦しいとことかない?」 「少し、ウエストが緩い気がするけど……」 「ゆるい? 普通なら、コルセットで強引に絞ったウエストで入るサイズなんだけど……さすがはレンタルボディってことね。人間離れしてるプロポーションしてるわ」 呆れ肩を竦める衣装係の娘。頭の先からつま先まで一通り見渡すと、隣で気付けを手伝っていた小道具の娘に、僕の顔にメイクを施すように頼んだ。 「この娘、メイキャップの腕は部内一だから安心していいわよ。絶世の美女からモンスターまで何でも仕立ててくれるから」 モンスターって……。それってメイクはメイクでも特殊メイキャップじゃないか。 言うだけあって、その腕は確かに見事だった。 鏡に映し出された僕の顔は見る見る内に変わっていく。 化粧の仕方など僕が知らなかったのもあるし、スッピンでも外に出ても見られるほどの美人の顔立ちだったこともあり、この顔に化粧なんて施したことはなかったんだけど……ドレス姿と相まった僕の姿は、別人と言ってもいいほど輝いていた。 「どう? 綺麗でしょ」 鏡の片隅で、僕にメイクを施した小道具の娘が胸を張ってる姿が映るが、今の僕の目には入っていなかった。 ただ、ただ、その姿に、自然と感嘆のため息が洩れる。 女性が化粧をし、おしゃれを楽しむ気持ちが少しだけ分かった気がした。 「これ……が僕?」 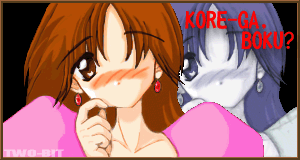 「『僕』は止めなさいって。舞台と同じで自分のことは『私』と言いなさい。その姿では、その方が自然よ」 「あっ……」 その言葉に、自然と小さな呟きが洩れた。 彼女が悪いわけではない。何も知らなかったのだ。性質設定の一つ、従順な性質が命令されてしまったことを受け入れてしまうことに。 ……この『私』が。 歯車を狂わすには十分な些細な命令だったことに。 舞台以外の場で頑なに守っていた『僕』と言う一人称は、私の男としての最後のアイデンティティだった。だけど、それも今はどうでもよかった。 ただ、この鏡に映った自分の姿を見ている間は…… ▽ 講堂に戻ってきた私を、感嘆の声で出迎えたのはケイだった。 「ふーん。さすがは俺の選んだ身体だ。見事に化けて見せてくれたものだ」 「宿っている私がいいからです」 「およ?」 私の返答に、キョトンと間の抜けた顔を見せたケイ。すぐにその顔にはコケティッシュな笑顔が浮かぶ。 「どう言った風の吹き回しなんだ?」 「この姿になって、少しだけ吹っ切れたんです。幕が降りるその時まで、薄幸の美少女を演じるものと割り切りましたから。そうでもしないと、青年将校とキスする度に、『僕』の精神が砕けそうですからね」 「ふーん。何はともあれ、何とか明日の本番には間に合いそうだな」 彼はそう言うとクルリと身体を舞台に返し、 「さぁ、みんな。休憩は終わりだ! 最後の練習にはいるぞ!」 4 セリフも覚え、演技も完璧にマスターし、そして、心の底から少女を演じることを認めた今、演劇は滞り無く進む。 残すところは問題のラストシーン。今までの稽古の中、私は自分の『僕(心)』を閉ざすことでそれを乗りこなす術を身に付けていた。 そんな時―― ぐらっ。 小さな揺れ。見渡せば緞帳が揺れていた。 「地震……」 観客には聞こえないぐらいの小さな呟きを洩らした瞬間―― 激震が舞台を襲った。 「キャッ!」 頭を押さえうずくまる私。 「危ない!」 「えっ!?」 同じく舞台に立っていたケイの声が聞こえたと思った時、私の身体に彼の身体が覆い被さってきた。 後に感じたのは重い衝撃。 私の意識は、そこで途絶えた。 ▽ 「う……ん……」 微かな揺れを感じ、私は目を覚ました。 余震でも続いているのかと訝ったが、意識がハッキリしていく内に、自分がケイの背の上にいることに気付いた。おんぶされていたのだ。 「ちょ、ちょっと! 何なんです!?」 「あまり揺らさないでくれ。お前をかばう時に打った身体がそこら中痛むんだよ」 ケイの言葉に、身体を動かすのを止めるが……現状がまったく理解できない。 キョトンとしてる私に、 「やっと気がついわね」 ケイと併走して歩いている部長さんが声をかけてきた。見れば、彼女は私とケイの分の荷物を持っている。 何がなんだか分からない私に、部長さんは今の現状に至るまでの経緯を教えてくれた。 突如舞台を襲った地震。背景が倒れるなどのアクシデントはあったものの、幸いにして地震はすぐに収まり、劇は最後まで行われた。信じられない話だが、倒れてきた背景の下敷きにあい一度は気を失った私――ケイが身を挺してかばってくれたが、運悪く倒れてきた背景の一部が突起しており、それに頭を強くぶつけていたらしい――だったが、すぐに目を覚まし、唖然としている周りを後目に、演劇を再開したそうな。そして、幕が降りると同時に、崩れるように再度気を失ったらしい。 医務室のメディカルマシーンの診断結果、ただの脳震とうとでた。それで、大事をとって部屋へと送る途中だと言う。 どうりで、今の私の姿はラストシーンで着ていたドレスのままである。 「劇……無事に終わったんだ……」 「ああ、お前のおかげでな。拍手喝采の大成功だったよ」 優しい言葉に、体の中で何かが跳ねた感じがした。 「どうかしたの?」 隣を歩く部長さんが覗き込んできた。 「いえ、別に。ただ、おんぶされたことなんて、小学生入る前以前のことだから……不思議な感じがして」 服越しにケイの体温が感じられる。 そんな彼の体温に、何故か心臓が逸る。 「あっ、降ろして下さい。一人で歩けますから」 「無理言わないの。頭はただの脳震とうで済んだけど、右足挫いているのよ」 言われて首を傾げて右足を見ると、スカートの裾の向こうに包帯が巻かれた右足首が見えた。 「そう言うことだ。それに、少しくらいは恩を返させてくれ」 素っ気ない言葉と共に、ケイはずり落ちかけた私の身体を再び上にあげるように身体を揺らした。 そんな彼に苦笑しながら、部長さんが話しかけてきた。 「ケイってば、照れてるのよ。さすがのこの娘も、あの地震で芝居を諦めかけたんだけどね、あなたが続行することを選び、見事に達成させたことに面を食らっているのよ」 「うるさいぞ、部長」 どこか照れを隠している叫びだが、部長さんは一切気にすることなく会話を続けてきた。 「ねぇ、あなた。この娘と付き合う気ってない?」 「ちょっと、部長!」 「付き合う? 彼と?」 あまりにも自然にケイのことを『彼』と言った私の言葉に、部長さんは小さく苦笑を浮かべた。 「もう、劇は終わったんだから、元に戻ってもいいのよ」 「あっ……はい。でも、まだドレスを着ていますから……上手く精神の切り替えができないので、これを脱ぐまでこのままでいますわ。それに、ケイさんも男性のままですし」 私の言葉に納得したのか、部長さんは更に話を続けた。 「今まで、何十回と劇をやってきたわ。中には別の大学の演劇部から男性部員を助っ人にまわしてもらったことも何回かあったんだけど、そのほとんどがケイのしごきには付いていけず、劇を降りたの。 でもあなたは違う。最後まで耐えきってみせた」 「それが何だと言うんです?」 彼女の言いたいことが分からない。 「劇にのめり込み、如何なる役でも真剣に演じるているうちに、この娘は本当の自分を見失ってしまったのよ。時には恋い焦がれる乙女の役、または恋を忘れた老婆の役をやる。恋する側される側はもちろん。男性だって子供から老人まで多数の役を演じた。さらには犬猫の動物から無機質な看板まで何でも本気でこなした」 「それって、俺がまるで芝居バカみたいじゃないか」 「見たいじゃなくて、そうよ。何の予備知識もなく男性の身体に押し込められて平然とそれを演じていられる人を、バカと言わずに何て言うのよ。 ――っとまぁ、んなことで、この娘には自分が無いのよ。舞台の上で自分を消せるのはかまわないけど、一般生活にまで自分を消して欲しくないのよ。だからね、恋人でもできれば本当の自分を取り戻すかなっと思って」 「うっ……」 小さな呟きがケイの口から洩れたのを聞き逃さなかった。 どうやら、図星のようね。しかも、自覚があるみたい。 ……でも、それを言ったら今の自分もそうなる。私は本来の自分を見失うことで今の『私』と言う存在を演じているのだから…… そんな私の考えを知ってから知らずか、彼女の話は続く。 「幸い、しごきに耐えきったあなたなら、この娘も気に入っていると思うの。それに、あなたもこの娘のことが気になっているでしょ」 「えっ?」 虚を突かれた言葉に、思考が一瞬停止した。 「ちょっと待って下さい。どうしてそう言う考えが浮かぶんですか」 「どうしてって言われてもね〜。ただ漠然とそう思っただけなんだけど……」 「だいたい、私も彼も、こんな身体なんですよ」 「それなら問題ないじゃない。明日には二人とも元の身体に戻れるんだから。それに、今のまま付き合っても男女の健全なカップルなんだから問題もないわね」 そうこう言っているうちに、私達はマンションの部屋へとたどり着いた。 地面に降ろされた右足が床についた時に軽い痛みが走る。確かに挫いているようだ。 「そう言うことで、少しだけでいいから考えてみて」 部屋の扉を開ける私に、そう言い残して去っていく部長さん。 そして、ケイは―― 「じゃあ、明日」 それだけ言って、隣の部屋に入っていった。 5 「おはよう。ケイさん」 マンションの前で僕はケイと待ち合わせをしていた。 無論、レンタル屋へ本来の身体を受け取りに行くためだ。挫いた右足は、張っていた湿布が良かったのか、一晩寝たら全快していた。 「あっ、おはよ。昨日はぐっすりと眠れた?」 「ヘトヘトに疲れていたからね。夢も見なかったよ」 たわいもない会話が続く。 この一週間、しごきにしごかれ少女を演じてきたのも、もう終わりかとも思えばそれとなく感慨深い。 今でこそミニスカート姿で街を歩くことにも馴れたが――覚めない夢は存在しない。 奇妙な夢はこれで終わる。僕は男に戻り、ケイは女に戻る。全てが自然の男女の形になる。 『この娘と付き合って』 昨日の舞台後に部長さんに言われた言葉が思い浮かんだ。 付き合ってくれと言われても、ハッキリ言って自分がケイのことをどう思っているのか分からない。好意が無いと言えば嘘になるが、それで付き合えるほどにケイという女性の存在を知らない。唯一分かるのは、男としての彼女のみ。 「何? どうかしたの?」 僕の視線に気付き、彼女がかぶりを振った。 ケイの言葉遣いは、僕と同じように舞台が終わり本来のものに変わっていた。そして、その仕草も―― 「昨日の舞台で僕を助けたのって、劇を続けるのため? それとも僕のため?」 「うーん」 口元に人差し指を添え、首を傾げるケイ。 「ほとんど無我夢中の行動でよく分かんないけど、しいて言うなら両方ね。あなたとの舞台が未完のまま終わると思ったら、無意識にあなたをかばっていたもの」 どうやら、ケイはケイなりに僕の存在を気にはかけているみたいだ。 「――ねぇ」 不意にケイの顔にコケティッシュな笑みに変わった。 「昨日部長が言っていたこと、覚えてる?」 「そりゃまぁ、覚えているけど……」 自然と顔が赤くなっていくのを感じた。 「恋人として付き合うかは別にして、元の身体に戻った後も、あたしと一緒に舞台に立ってくれないかな。あなたと演劇をやるのって、楽しかったから」 「少し――」 一拍おいて、 「少し、考えさせてくれないかな。この身体でいると、正常な答えが出そうにないんだよ」 僕はそう答えた。 いや、この身体としての答えは出ていたのかもしれない。ただ、それには条件がいる。 そして、会話のないまま二人はレンタル屋の前までやってきた。 真っ直ぐに入り口の扉を見つめていると、 ――もう少し、本当の自分を出してみればどう?―― 初めてケイとこの場で会った時の言葉が思い出された。 ケイの言う、本当の自分とは何なのか? それは分からない。ただ、嘘と偽りのこの体の中で、僕の魂は何の隠し立てのないさらけ出した自分だったのかもしれない。 色々と考えながら扉をくぐろうとした僕を、ケイが止めた。 そして、彼女は指さす。自動ドアに張られた一枚の紙を―― 『都合により、閉店します』 ▽ それから、二人して周りの人に聞き込みをした結果、僕達の事故以降もレンタル屋では事故が勃発し、それが公に公表され、営業権利を無くし閉店したのだと教えられた。ニュースで取り上げられもしたらしいが、演劇の練習で忙しかった僕達の知るところではなかった。 さらに、デジタル変換して保管してある利用者の身体は、コンピュータウイルスに犯され、形を成さないことを知った。今、ボディレンタルを行っていた会社の親会社が、ウイルスの汚染を除去しているらしいが、それさえもいつになることやら…… つまり、僕達二人は、今しばらくこの身体でいなければならなかったのだ。 「――ねぇ」 隣で同じように閉まっているレンタル屋を見上げているケイに呼びかけた。 「さっきの答えなんだけど……舞台に立つのはかまわないわ。ただし、この身体に性質設定を希望したのはケイさんなんだから、ちゃんと元の身体に戻れる時まで責任もって守ってくれると約束してくれるならね」 上目遣いの視線を向け、僕は笑って見せた。時折見せるケイのコケティッシュな笑みを真似て。 そんな僕――私に、ケイは困ったように微苦笑を浮かべ、私の顎をそっと持ち上げた。 それが、演じている役割としての少女ではなく、まして男でもない――自然な女としてのファーストキッスだった……のかもしれない。 −The End− |